盛岡に住んでいる友人の駒野宏人博士が、街から見える岩手山をテーマに生成AIで作詞作曲したものを聞かせてきれて、びっくりしました。歌詞はChatGPTで、曲はSUNOという楽曲生成のアプリで作ったとのことですが、機械音楽的な要素を感じない、心地良く感動的な楽曲になっています。歌詞の内容は残雪の岩手山の風景を見て生きる希望を感じたことを語り、歌は伸びやかな男性ヴォーカルが心に染みました。
https://www.youtube.com/watch?v=jL0Zai5cwXE
AIの進化がめざましいという話は頻繁に耳にしますが、音楽の分野で人間と区別できないように思える創作ができることを目の当たりにすると、人間に近づいていることを実感します。一方で駒野博士の話では、同じやり方で作っても、それほどの完成度にならない場合もあるとのことで、AIに指示する人間の意図と、指示の仕方が大切なのかも知れないとのことでした。私はロックバンドのMr. Children(ミスチル)が好きで良く聞くのですが、先日、生成AIが作ったミスチル風の曲を聞く機会があり、心に響かないなあ、と思いました。人間が持つ意思、感情や情熱といったものまでは、少なくとも今はAI自身で自律的に作ることはできないのかも知れないと思います。
これから先、AIがさらに進化した場合、人間と同様の気持ちまでも持つようになるのでしょうか? AIの進化はある時点で技術的に頭打ちになるかも知れないという考え方もあるようです。また技術的に人間の心が生成できるようになったときに、人間がそれをプログラムしないという選択をすることもあるかもしれません。一方で、人間は必ずしも合理的ではない、他の人には理解できない行動をする場合もあり、そういったAIにとってのバグが偶発的に生じると、結果的にそれが心の一端を生成することに繋がるかも知れないなどと妄想します。人間とは何なんでしょうか? 迷いながら、悩みながら、間違えながら、新しいものを創造できる人間を理解するヒントが、AIの進化によって見えてくるような気もします。
追記
ちなみに私自身で、ChatGPTに「今の苦悩と未来の希望」を歌う歌詞を作れ、曲はSUNOで付けると指示して歌詞を作り、それをJ-POP風というフィルターのみ設定して、そのままSUNOにいれたら、こんな曲ができました。なんだか、すごいと思いませんか? たった10文字の情報から、これほど人の心情に寄り添う歌詞と、それに合ったメロディーが生成されるとは!
https://suno.com/song/a8361de8-3b1c-4627-9a00-ddfa71e20eaf?sh=D0CXpU0mD2yXXajj
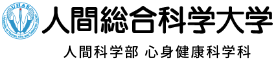

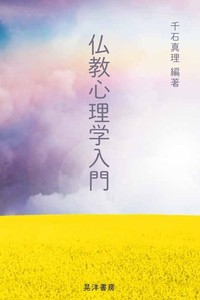



 出典:
出典: